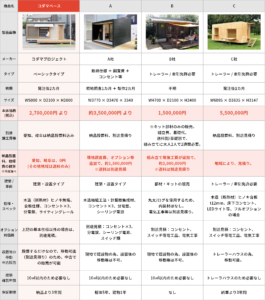私は今、車の中でこの原稿を書いています。 家の敷地内の駐車場に止めた車の中で(笑)。
「家の中でやればいいじゃん!」と思いますよね? しかし、暖かくなってきたこの季節、部屋の中より外のほうが断然心地よく、原稿仕事もはかどるんです。

自宅の駐車場ならWi-Fiもつながりますし、何より個室感があって集中できる! よくカフェで仕事をする方を見かけますが、私は無理。隣の人の会話や、誰が何を注文したのか気になってしまうんです。
そんな話はさておき、今回ご紹介するのは、車一台分の駐車場スペースがあれば設置できるタイニーハウス「コダマベース」です。
「コダマベース」とは?
「コダマベース」は、国内の針葉樹を有効活用しながら、人の心にも体にも優しく、使い勝手の良い小屋を作ろう! というコンセプトのもと誕生しました。
タイニーハウスが日本で注目され始めた2018年頃から、私はさまざまな会社が手がけるタイニーハウスを取材してきました。その中でも、「コダマベース」は特に細部へのこだわりが行き届いていると感じました。

そこで今回は、私の“勝手にランキング”形式で「コダマベース」の魅力をお伝えします!
インスタはこちら➡https://www.instagram.com/
◆ 1位:ライティングレールが標準装備
スポットライトやペンダントライトなど好きな照明を取り付けられるのがいいなと思いました。照明をどこにいくつ設置するかで、好みの空間が作れそうですよね。

◆2位:ベンチにもなる窓枠
これはもうデザインの勝利!
「コダマベース」には大きな窓と小さな窓が付いています。大きいほうの窓枠は30センチほどの奥行があって、ここがベンチとして使えるのです! 外の景色を眺めながらコーヒーを飲むとか、ゆったり読書をするとか、日向ぼっことか・・・。そんなシーンを想像して、これはいいぞ!と思いました。

ペアガラスになっていて、窓を閉めれば外の音が気にならないうえ、外気の影響を受けにくいという造りになっています。オリジナルで網戸がついているのもいいなぁと思います。
しかも、窓はペアガラス仕様で、断熱性が高く外の音も気になりません。オリジナルの網戸付きで、開ければ風通しも良好です。
ちなみに小さいほうの窓は、ペアガラスの扉と内開きの網戸。風が通りやすくなるので空気の循環ができます。

◆3位:DIYもできる頑丈な壁
「コダマベース」の内装は国産材の東濃ヒノキ。床材もヒノキの無垢。壁はヒノキの積層合板でできています。厚さが12mmあるのでどこでもネジが効くのがいいですね。

ハンモックや収納用の棚を付けたりもできるし、ギターハンガーをつけて楽器を収納しながら飾るとか、いろいろ考えるのが楽しくなりそう。壁の強度があるからできることだなと思います。
自分好みにカスタマイズできるのが楽しいポイントです。

◆4位:真鍮のスイッチプレート
これ、入って真っ先に気になりました。スイッチのプレートが真鍮製なんです!オプションかなと思ったら、標準装備。アンティークな雰囲気が好きな私にはたまらない!
空気に触れたり手の油に反応したりして、独特の深みを増していく真鍮。細かいところだけれど、スイッチは毎回目に触れるところ。こだわりが光っているなと感じました。
ちなみに、コンセントは室内に3カ所つけることが可能。好きなところにつけられるというのも、好きな位置に取り付けられるのも自由度が高くて◎。
◆5位:ヒノキの香り
「コダマベース」のなかは、とにかく気持ちがいい!
ドアや内装などヒノキの無垢材が使われているから、ヒノキの香りに包まれるんです。森にはいったときみたいに深呼吸したくなる気持ち。鎮静作用があるヒノキの香りと質感、手触りなど、リラックスできます。

5位まで挙げてみました。デフォルトでもけっこう満足な内容だと思いますがいかがでしたでしょうか。
デフォルトでも満足度の高い「コダマベース」ですが、オプションでウッドデッキやロフトを追加することも可能。
こんな快適な空間なら、仕事もますますはかどりそうだな〜と、車の中で原稿を書きながら改めて感じたのでした。

【参考】
コダマベース https://kodama-p.com/category/item/architecture/
YouTube