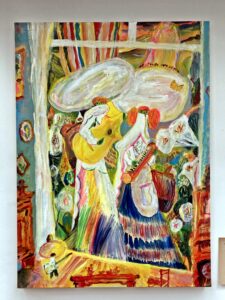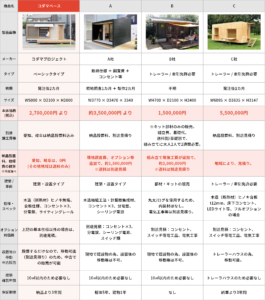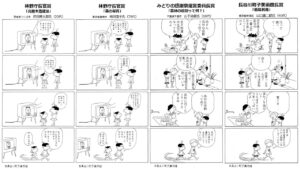里山で工房体験ができる「駿府の工房 匠宿」
源氏・今川氏・徳川氏ゆかりの史跡が残る静岡県静岡市駿河区の丸子(まりこ)。東海道五十三次の20番目の宿場「鞠子宿」として有名ですが、そこから車で5分ほどの場所にある泉ケ谷(いずみがや)というエリアを散策してきました。

泉ケ谷は10年ほど前に訪れたことがあるのですが、その時にはなかったおしゃれなレストランやゲストハウスなどができていて里山の自然+モダンといった雰囲気に進化していました。
今川氏に使えた連歌師・宗長がおこした寺「吐月峰柴屋寺(とげっぽうさいおくじ)」、樹齢300年以上という大銀杏の丸太が見どころの「千手観音堂」など歴史的なスポットも点在していますが、なかでもたくさんの人で賑わっていたのが「駿府の工房 匠宿」です。

隈研吾氏監修のスツールを自分の手で
「匠宿」は国内最大級の伝統工芸体験施設。竹細工や和染め、木工、漆や陶芸など、さまざまな工芸体験が用意されています。工房をチラッとのぞいてみると、楽しそうに“マイ箸”を作っている子どもたちがいたり、慣れない手つきで電動ろくろをまわしながら土を成形しているカップルがいたりと、みんな楽しそうです。
さらに奥へ進んでみると、「匠宿伝統工芸館」と書かれた場所があったので入ってみました。メインで展示されていたのは隈研吾氏が監修したスツール「タテヨコナナメ」というもの。

隈研吾氏と言えば、木材をふんだんに使用した建築で世界的にも知られている建築家です。2021年の東京オリンピックのメインスタジアム・国立競技場の設計をしたことでも有名ですよね。
そんな隈研吾氏が「匠宿」のために設計したのが「タテヨコナナメ」なんです。最低限の構造でできた本体に、3本の木材を取り付けて完成させるスツール。3本をどこに取り付けるのかは使用者の自由というデザインです。「匠宿」では、このスツールを自分で作ることができる木工特別体験プログラムも開設しているそうですよ。

HPには隈研吾氏のメッセージが掲載されています。
| 「子供から大人まで楽しめる『育てる』スツールをデザインしました。
最初は不安定なスツールが、木の材料を補強していくことで人を支えられる程に強く育っていきます。 一本一本は小さく強度のない木をたくさん集めて強い建物を作る、日本古来の木造技術を学び体験できるスツールです。(後略)」 |

デザインの斬新さだけでなく、強度や使い勝手などを自ら考えるツールなんですね。
地元・静岡のヒノキを使った贅沢な質感、木の香り、そしてデザイン—。自慢したくなるようなスツールが完成しそうです。
自分が使う道具(家具)がどのような素材でどうやって作られるのかを知ることはとても有意義なこと。子どもの場合、小さなうちから実体験として身についていると、その先のモノの見方がずいぶん違うだろうな~と思いました。

ギャラリーで目に留まった一枚板のテーブル
ほかにも、施設内にある「ギャラリーTeto Teto」では、民藝品、工藝品のほか普段使いができる日用品まで、ものづくりの粋を集めたアイテムが展示・販売されています。
お土産やプレゼントにしたいアイテムがたくさん並ぶなか、私の目が釘付けになったのは、一角にど~んと置かれた一枚板のテーブルです。


このカーブ、厚み、なんという存在感。立派ですよね。重厚感といい、艶と色、手触りといい…。憧れのまなざしで何度も見てしまいました。
ショップの入り口には隈研吾氏デザインの「TSUMIKI」が販売されていましたよ。

里山の自然に囲まれて、匠の技を身近に感じられる「駿府の工房 匠宿」。
ファミリーや友達と一緒に行ってみてください!きっと楽しい体験ができますよ。

【協力・画像提供】
駿府の工房 匠宿
https://takumishuku.jp/index.html
【参考】
丸子まちづくり協議会
国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所
「東海道への誘い」
https://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/tokaido/index.htm