いきなりですが、このピンクのカップボード個性的ですよね。実は無垢材で作られたヴィンテージ家具をリメイクしたものなんです。

とあるご縁で仲良くさせていただいているsoiro living(以下soiro)さん。家具のリメイクやDIYサポートなどを手掛けていらっしゃるのですが、今回はリメイクが完了した家具の納品があるということで、同行させてもらうことに。
何のリサーチもなく同行したのですが、現場で完成品を見て驚きました。ポップでかわいい! 実は、納品した場所はヘアメイクやエステなどを行っているサロン。壁紙も紫やペールグリーンなどポップなカラーでまとめられていて、なるほどここならピッタリ!といった感じでした。
ポップな色に生まれ変わったカップボードですが、元の姿はこちら。

知り合いから譲りうけたものの、どう使うのがいいかずっとアイデアを練っていたというオーナー。soiroさんに相談を持ち掛けたのは2年ほど前。色や形など、じっくりとすり合わせをしながらリメイクを進めていったそうです。

もともと上下に分かれる仕様だったため、上段部分の奥行を減らし、引き出しだった部分をカット。下段との間に空間を作りました。引き戸だった収納部も扉に変更、土台部分に足を付けたことで、どっしりとしたシルエットがかなりすっきり。ヨーロッパの家具のようなシルエットに仕上がっていました。

ヴィンテージの家具がなぜか集まってくる(羨ましい!)というオーナーさん。サロンにはほかにもチェストや椅子など、ディテールに凝ったものが置かれていました。
ポップな家具と重厚なヴィンテージの色味は、相反するもののようですが、壁紙やほかの家具とのバランス次第ではうまくマッチするのだな、と感心してしまいました。

「家具は手入れをしたり作り替えたりしながら、長く愛着を持って使ってもらいたい」というsoiroさん。暮らし方や自分らしさは変わっていくもの。家具もそれに合わせてアップデートしていくことが必要になってきます。
合わなくなったから捨てるのではなく、どうやって使っていくかを考えていきたいものです。
今回のカップボードがこうしたリメイクを施せたのは“本物”でできていたから。無垢材でできた家具であれば、強度を保ちつつ形を変えることが可能です。
なぜ無垢材がいいのか、という理由はそんなところにあります。買った時だけでなく、作り替えたいときにも本領を発揮してくれるんですね。
次回、家具のリメイクやDIYについてもう少し詳しく紹介していきたいと思います。(ま)
【取材協力】
soiro living































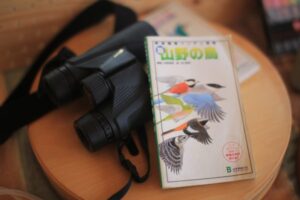
-088-200x300.jpg)




